今年の梅雨明けは例年より大分早かったらしい。雨の苦手な刀剣達にとっては幸いな事この上ない。
日中の空気は既に夏の気配をどことなく孕んでいて、潤う風に吹かれる草木は、一様に鮮やかさを増していた。
裏山の木々も、青々とした葉で溢れる枝を、のびのびと四方に伸ばしている。
馬の脚にかすって、身を乗り出していたホタルブクロの花がゆらゆら揺れた。
「いやー、久々の遠乗りは気持ちが良いね。」
既に真上に差し掛かった太陽を見上げた主に、前を行く今剣が馬上で振り返った。
「はい!雨ばかりでたいくつだったので、馬たちもよろこんでますよ!」
ぶるる、と今剣の乗る青海波が応じるように鼻を鳴らす。
「俺お腹すいちゃったな。そろそろ昼にしよーよ。」
相乗りしている蛍丸が、手綱を握る主の腕の中からマイペースに声を上げる。
「そうだね、先の原っぱで昼にしようか。良いかな倶利伽羅?」
後ろを振り返ると、大柄な鹿毛の馬上からチラリと視線を寄越した大倶利伽羅がフンと鼻を鳴らした。
好きにしろ、という事らしい。
彼は梅雨入り前にこの本丸に来て早々、哀れな事に審神者の悪戯の餌食になった。と言っても、その時ばかりは後ろに堀川という黒幕が居たのだが。しかし、そんな事は関係ない。彼にとっては、いきなり呼び出されと思ったら、問答無用でズボンを剥ぎ取られ黒ボクサーを晒される、という屈辱を味わった事が全てだ。
彼女はこの一ヶ月で、漸く彼との関係を死に物狂いでマイナスからゼロに戻した。あの事件(今では下着事変と呼ばれている)の直後、堀川は2人の兄弟を巻き込んで、彼女と一緒に反省という名目で裏山に逃げ込んだ。そうして彼らが3日間の山籠もりから帰ると、石切丸?歌仙?一期?燭台切という面子がそれはもう良い笑顔で待ちわびており、恐らく主はこの本丸に来てから一番反省した。
堀川も同じく説教されていたが、山籠もりの間にそれまで全く気配のなかった和泉守兼定が遠征先から連れ帰られていた為、心ここにあらず、どころではなかった。誰もが反省させることを諦めるくらいの桜吹雪であった。
そういう経緯があって、久しぶりの遠乗りに駄目元で大倶利伽羅を誘ってみた審神者は、予想したよりかは快諾してくれた彼に内心で胸を撫で下ろしたのであった。
降り注ぐ陽光の下で青海波と高盾黒がお互いのたてがみを、はむはむと毛づくろいし合っている。
思い思いの場所に腰掛けた4人は、燭台切が嬉々として持たせてくれた弁当に舌鼓を打っていた。
「重箱の弁当って???完全にピクニックだね。」
「ぴくにっくってなんですか?」
「野外で食べる食事を持参した遠足、といったところだね。」
「んー!梅干しすっぱ!」
和気あいあいとした3人から少し離れた倒木の上で、大倶利伽羅がこちらに半分背を向けて無言で握り飯を咀嚼している。これでもかなり打ち解けてきたのだ。ちょっと前までは、例えるなら『少し顔馴染みになった半野良の猫をうっかり驚かせ怪我させてしまって、家に連れ帰って同居している』状態であったのだから。
せめてもの救いは、短刀達には悪戯の詳細が明らかにされなかった事と、同じ悪戯をした他の面々とはさほど関係が壊れなかった事か。
逆に、共に山籠もりした2人とは親睦が深まったくらいだ。同じ仕打ちをしたのに何と心の広い男だ、と審神者は思わず感涙しながら2人を抱擁した。残りの国広はまだ許していない。
「このまま、まったり中腹の開けた所まで行こうよ。この天気ならきっと夕焼けが綺麗に見えるよ。ちゃんと灯りも持って来たから、帰りもダイジョーブ。」
手に付いた米粒を舐めながら蛍丸が言う。
「わぁ、いいですね!そうしましょうよ、あるじさま!」
横から勢いよく腕にしがみついてきた今剣を宥めながら、審神者は大倶利伽羅を窺った。
「…好きにしろ。」
とっくに食べ終えていた大倶利伽羅は、さっさと立ち上がると自分が乗って来た松風の方へ歩いて行ってしまった。
「あいかわらずですねえ。」
「ツンデレってやつでしょ。そんなんで気を引こうったって無駄なんだから。」
「んー、デレたとこ見たことないけど。」
「別に見たくなんかないんだからねっ。」
「それだと蛍丸が倶利伽羅に気があるみたいになりますよ?」
「うええ!ないない!俺は主が好きなの!」
「あ、ぼくもですよ!」
「両手に天使!パトラッシュ、ぼく幸せだよ…。」
「パトラッシュって誰?異人?男?」
「はい、大太刀はそこに置いといて。そのパターンもう飽きたから。」
「チッ」
「天使は舌打ちなんてしない…」
「さーあるじさま、なかまはずれの大倶利伽羅がすねないうちにいきましょう。」
「はーい。」
カツカツと蹄が石を弾きながら進んで行く。細い山道も馬達は慣れた様子で、安心して身を任せられる。
「そういや、この馬達も所謂”神獣”みたいなものかね?」
ふと思いついて審神者は問うてみた。
「そういわれると、そうですね。すがたが当時とだいぶ違いますし。」
「何かおっきくなっちゃってさー。ずるいよね。」
「あ、やっぱりそうなんだ。当時の在来馬ってポニーサイズだったもんね。暴れん坊将軍、めちゃくちゃ膝曲げて乗らなきゃいけないとか格好悪い。」
「昔の日本男児の平均身長だったら普通に乗りこなせるけどねー。…ぶふっ!」
「どしたの蛍丸?」
「いやー、大倶利伽羅がすごい頑張ってポニーに乗って戦場を駆けるところ想像したら…」
「ぶはっ、こらやめてよ、っふ、かっこいいでしょっふ???っ」
「燭台切だったら、かっこよくのれそうですね!」
「「ブッハ」」
「きまってる!きまってるよ光忠ぶふー!」
「主、ツボり過ぎだよっ!っふは!」
「…っあ、やば、また倶利伽羅の好感度ゲージが!」
慌てて振り返った視線の先で、大倶利伽羅が片手で口元を覆いながら上半身を右に捻っていた。よく見ると肩が小刻みに震えている。
「???あの人、意外に笑いの沸点低いんj「シャラップ!HOTARUMARU!ゲージを下げないで!」
素早く蛍丸の口を押えた審神者は、またしても内心で安堵の息をついた。あいつ普通に良い奴なんじゃないか。
「いやまぁ、何にしても、サラブレッドサイズでありがたいわ。それに乗馬初心者の私でもすぐ乗れるような優秀な子達だしね。」
「あるじさまは どうぶつがすきですね!」
「うんうん。生き物は良いね。私は土壌生物から鯨まで平等に好きですよ。」
「嫌いな動物はいないの?」
「え?人間。」
「わあ、何か凶悪な顔してた。」
「きかないほうがいいやつですね。」
「そうだね、聞かなかったことにして。」
「「はーい。」」
道の途中途中で、花や動物を見付けては立ち止まり、一行が山の中腹に辿り着いたのは、計らずも日没の頃合であった。
開けた木々の間から、遠い山々の影にゆっくりとその身を沈めつつある太陽が見える。
馬をそれぞれ手近な木に繋いだ今剣と蛍丸が、人間離れした動作でひょいひょいと大木の中程まで登って行った。
ちらりと視線をやった審神者だが、注意を促す必要もないのは今まで共に暮らしてきて嫌という程知っている。
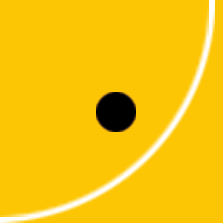
暮れなずむ光の、未だ届く所だけが鮮やかな茜色に染められ、その中に自分達も含まれていた。
「綺麗だね。」
ぽつりと落ちた言葉には誰の答えもなく、けれど審神者はそれを無礼とも思わなかった。同意を求めた訳でもなく、また、こういう風景を前に言葉は反って無粋であるとよく知っていたからである。
自分達が登って来た道はとうに陽が当たらず、闇に身を潜めていた。彼女が少し前まで暮らしていた世界では、そう身近にはなかった光景だ。それを見下ろしていると、子供の頃に誰もが一度は感じた事のある、所謂”正体不明の畏怖”を今でも感じる。
皆に置いて行かれて慌てて走った夕暮れの帰り道、ふと覗き込んだ路地裏の空気、誰かを驚かそうと息を潜めて隠れた押し入れの中。
あの暗闇の中には一体、何が居たんだろう?決して目には見えない、けれど確かにそこには何かの気配があった。
もしかしたら、ある種の物の怪や付喪神の類だったかも知れない。今こうして神々に囲まれて生活する身には、あながち妄想とも思えなかった。
「???人間のどこが嫌いだ。」
突然、物思いに耽っていた耳に、低い声が届いた。消えゆく光から目線を離さない横顔を見上げる。
「…本気にしたの?」「嘘なのか。」
間を置かず、また質問が投げられた。
暫く黙って同じ方向を眺めた。
一度二度、ちかっちかっと瞬いてから、太陽が完全に山に飲み込まれる。今度は残照が雲を染めてその存在を証明した。
「倶利伽羅は人間が好き?」
「????。???質問に質問で返すな。」
急激に闇色に染まりだした風景に、大倶利伽羅の褐色の肌も溶けていく。
「まぁ、そこらの普通の人よりかは人嫌いである自覚はあるねぇ。」
「どうしてだ。」
珍しく会話が続く。
「さっき貴方が言い淀んだうちに考えた事と、そう変わらない理由だと思うよ。」
「????。」
いつの間にか暗闇から黄金色の瞳がこちらを向いていた。
「人間てのは奇妙で愚かで面倒で、難解な生き物だよ。」
「????。」
「こんな生き物に落とされて、神サマも憂鬱よなあ。」
冗談めかしてからから笑うも、大倶利伽羅は--再び目を逸らして答えなかった。
「ぼくはいやじゃないですよ?」
急にぐいと腕を引かれた。今剣がいつの間にか木から降りて来ていた。
「俺もそんなに悪くないよ。」
反対の腕に同じように蛍丸が巻きついた。
「あるじさまと、こうやっていろんなことできるんですもん!」
「そーそ、自分の手で武器振るうのも食べるのも遊ぶのも話すのもお風呂も寝るのも楽しいよ?あと主をこうやってぎゅーってできる!」
今度は腰の辺りに勢いよく抱きつかれる。確かな体温が服越しに伝わって来た。
「おぅおぅ、嬉しいね!殿様気分だよ。」
「俺らを侍らせてどうするつもりですかぁ~?」
「何それ宗三の真似?似てないよ!」
けらけらと、ふいに屈託なく笑ったのが久方ぶりな気がしてしまい、審神者は心の内で苦笑する。こんな性格でも、人の多い本丸では無意識に色々セーブされているらしい。
???いや、常に頭の片隅に巣食っている、本当の心配事が自分をそうさせているのは分かっていた。政府から配布された資料の、一番下にあった刀剣男子の名前がちらと過って、審神者はそれを静かに消した。
「???さて、ぼちぼち戻ろうか。」
すっかり陽光の気配も遠くなり、夏虫のジーという声だけが断続的に聞こえる。夜目の効かない身には他の3人の影はおぼろげにしか映らない。
はーい、という返事と共に弓張り提灯に次々と灯りが灯された。明かりがあるというだけで途端に心強くなる。
蛍丸に助けられて馬上に上がると、高盾黒が任せろ、というように鐙に引っ掛けたつま先を食んだ。軽く首筋を叩くと、提灯を揺らしながら勇ましく歩き出す。すっかり慣れた振動が心地良い。
「あしたもきっといい天気ですね!星がすごくきれいです。」
今剣の浮かび上がる影が、弾んだ声を出しながら揺れる。釣られて見上げた空には西暦2205年では到底見られない光景が広がっていた。此処へ来て最初に見た時には言葉では言い表せない感動を覚えたものだ。
「本当だね。もうすぐ七夕だし、天の川が見れると良いね。」
「おー、七夕に笹持って来て本丸に飾ろうよ。んで、みんなで願い事書いて吊るす!」
「わあ!たのしそう!ぼくもやりたいです!」
「願い事、ね。うん、良いよ、やりましょう。」
わっと2つの歓声が上がり、少し驚いた馬が首を振った。
本丸まであと僅かの麓に下りて来た時、前を行く今剣があっ、と声を上げて馬を止めた。
「何?どうしたの?」
何事かと問いかけながら近づいた審神者に、今剣は興奮気味に指を差した。
「あるじさま!蛍です!あんなにいっぱいいますよ!」
指差す先に目線をやった審神者は、今度は目を凝らさなくても彼の示すものを難なく認める事が出来た。
無数の黄緑の光が、淡い尾を引きながら四方八方へ明滅を繰り返して乱舞していた。
「わわ!俺別に怪我してないよ!」
目の前を横切った光に、蛍丸が思わず弁解した。
「あぁ、この奥に沢があったね。そこに集まってるんでしょう。今が最盛期だものね。ちょっと寄り道しようか?」
気紛れな提案をしてみれば、先と同じように2つの歓声が上がった。道を逸れて歩き出した2頭に、3頭目も黙って従った。
馬を曳きながら辿り着いた沢には、幻想的としか言い表せない光景が広がっていた。
先とは比べ物にならない数の光が、ぶつかりもせず入り乱れて、時折水面すれすれを淡く照らしていた。
じっと見入っていれば、すぐに自分達もその風景の一部と思われたか、灯りは恐れもせず近くを通り過ぎていく。
「うん、壮観だけど流石に本を読める明るさではないね。」
急に昔習った故事が浮かんで思わず呟くと、手に止まった蛍に目を輝かせていた今剣がこちらを見上げた。
「ほん、ですか?」
「蛍雪の功という故事の話。昔の中国の話でね、貧しくて明かりの為の油も買えなかった苦労人2人が、それぞれ蛍を集めた光と雪の明かりを使って勉学に励んで、後にその二人は大成した、という話だよ。たいへん苦労して学問にはげみ、それが成功して報われるという意味の故事成語。」
「うわー、主が文系みたいなこと言ってる。」
「いや、私消去法で言ったら文系だし。いや、寧ろ右脳派?」
「うの???」
「直感的、芸術的、個性的ってな感じよ。」
「あぁ、山伏と歌仙を足して2で割ったようなってこと?」
「なにそれこわい。うん、私は何系でもないわ、そんな枠で括れない存在です。」
「かっこいいです!あるじさま!」
「純粋な人が居て良かったね、主。」
「せやな。」
すい、と指先から光が飛び立った。
「何か俺の所にだけすごい寄って来てない?」
「わ、本当だ。やっぱり何か惹かれるものがあるのかね。」
地べたに座り込んでいた蛍丸に目を向けると、なるほど他の3人より柔らかな光にたかられていた。
さながら優しい光のクリスマスツリーといったところか。
「ねぇねぇ!さっきの蛍雪のなんとかやってみたい!いっぱい集めて連れて帰ろうよ!」
急に大きな声を出した蛍丸から、幾つか光が宙に逃れた。
「えぇ…いや、見た感じ無理だよ。それに昆虫は繊細なのよ、すぐ弱っちゃうんだから。」
「試したらすぐ逃がすから!薄い麻袋が何枚かあるし!子供の好奇心を頭ごなしに殺さないでよお母さん!」
「産んだ覚えはねぇ!どうしようお父さん?」
「???。」
「ノリ悪ぅ。」
「やめい蛍丸。ごめんて倶利伽羅。」
「ぼくもやってみたいです!ははうえさま!…わ、なんかちょっとはずかしいですね…へへ…。」
「おk。優しく捕えて速やかに持ち帰ったのち、つぶさに観察を行い、直ちに放流します。」
「うわー何か納得いかなーい。」
「この純粋培養…同じ三条でもあいつ…!」
「石切パパに告げ口してやるー。」
「蛍丸様、心ゆくまで集めて速やかに帰還しましょう。」
「よきにはからえ。」
こうして淡く光る麻袋を隠し持った4人は、すぐ夕飯出来るよー、と出迎えた燭台切に曖昧な微笑みを浮かべ、審神者の執務室へ滑り込んだ。自室に戻ろうとした大倶利伽羅は、一蓮托生と微笑んだ演練の悪魔に、より一層の無表情で付き従った。幸運にも初期に鍛刀された練度の悪魔が戦場で与えた衝撃は、それなりのものだったらしい。
「どれどれ。」
早速、手近な書物を開いて麻袋を近付けてみるも、まぁ結果は予想通りだった。1匹1匹の光は微々たるものだし、何しろ常に光っている訳ではない。
「はい、無理でした。」
「ん~ざんねんでしたね。」
「だねー。でもまっ、スッキリしたよ。」
「そりゃ良かった。」
麻袋の中で蛍達が右往左往している。
「そういえばこの蛍、種類はゲンジボタルだね。今剣も中々の数に囲まれてたのは、仲間と思われてたのかもよ?」
「え、そうなんですか?」
審神者の言葉に灯りを見詰める瞳がかすかに揺れた。
「昔の人は蛍を死者の魂だと考えてたよ。」
脈絡もなく話し出した蛍丸に3人分の視線が集まる。麻袋の入り口を緩めて差し入れた手に、慌てた蛍がぶつかって止まった。
「前の主人に使われてた時、俺の怪我を治しに来てくれたのは阿蘇家の先祖の魂だったのかなって思う。別に源氏の人達だけじゃなくて、それぞれの御先祖様とか近しかった人の魂が、様子見に来てくれてんじゃん?心配性だね。」
口元に穏やかな微笑みを浮かべた蛍丸の手元から、すると擦り抜けた光が1つ、明滅しながら部屋を舞う。
ゆっくり弧を描いて目線の高さに差し掛かったそれを、今剣が両手でそっと包んで引き寄せた。
指の間から僅かな光が漏れては消えてを繰り返している。
「夕食できたよ…って何?明かりも付けないで、うわっ!」
引き戸を開けて顔を覗かせた燭台切が、乱暴に閉め直された扉に驚いて飛び退った。
「???取り込み中だ。」
ぶっきらぼうに投げられた言葉に、部屋の中の3人がぽかんとする。一人離れて、壁にもたれたまま座る彼の表情は見えない。
しかし、次に顔を見合わせて笑ったそれ以外の顔なら、暗闇でも見ずとも分かった。
「とりこみちゅうでーす!」「でーす!」「ごめんね、先に食べてて。」
次々に飛んできた声に、燭台切は溜息をついたようだった。それから「冷める前に来るんだよ。」と釘を刺して去って行く。
もう一度顔を見合わせて笑った拍子に、蛍丸の手元からふぁっと光が上がっていった。
「あ」
全開された麻袋から、閉じ込められていた蛍達が1匹、また1匹と自由に逃れ出す。
「???綺麗だね。」
「うん。」
まるで映画のワンシーンのようだ。捕まえる事も忘れて呟くと、今度は誰かの答えがあった。
儚い光の残像が、まるで自分達に語りかけるように描かれては消える。
その光に、きっと誰もが誰かを想っていた。
「ここから放してあげようか。沢までそう遠くないし、ここには池もあるしね。」
審神者の提案に今剣が立ち上がり、畳に降りた蛍を慎重に避けながら障子を開け放つ。月のない夜空が広がっていた。
蛍丸が無言で残りの麻袋の紐を解く。
「寧ろ此処が黄泉の国かしらね。」
中々出て行かない灯りを纏って主が笑った。
「死後の世界がこんな浪漫的な場所なら悪くないね。…ほら、お行き。」
蛍丸の言葉に、突然思い思いに飛んでいた灯りが意志を持ったように揺らめいた。
一拍置いて順々にふわりふわりと中庭へ飛んで行く。
「…不思議な事もあるものね。」
「刀が人になって話してるよりかは不思議じゃないよ。」
その答えに、審神者は思い切り声を上げて笑った。
流れていく光を追って、小さな体が2つ縁側に飛び出していく。大きく大きく手を振って、徐々に減っていく灯りを見送っていた。
思わず立ち上がって、そちらに一歩踏み出した審神者の眼前を、淡い光が横切った。
釣られるように追って振り返ると、それはふわふわと飛んで、変わらず壁にもたれたままの胸に着地した。
止まられた本人は微動だにしない。
足元に気を付けながら審神者はゆっくり歩み寄る。灯火は鼓動するように左胸で明滅を続けていた。
そっと覗き込むと気配を感じたか、光の間隔が早まる。
審神者がゆっくり手を伸ばす。小さな命に触れよう、というところで、ふいに横から手首を掴まれた。
間近で黄金色の瞳と見詰め合う。普段と変わらぬ無表情だが、何となく、思っている事は分かるような気がした。
「切ないね。」
言葉足らずにも程がある、と自分でも思ったが、大倶利伽羅の瞳は肯定するかのように揺らいだ。
掴まれていない方の手を差し出すと、またゆっくりと光り出した蛍が、心得たように指を伝って上って来た。
その手を2人の顔の間にかざしたまま、審神者は笑う。
「心配しなくても大丈夫、此処の皆は私が必ず守ります。惜しむものなんて何もないわ。」
今度は表情筋がちゃんと動いて目の前で瞠目して見せた。
その顔に、にしし、という表現が合う笑い方で、審神者はずいと己の顔を近付けた。
「人間てのは奇妙で愚かで面倒で、でも、どうしたって愛おしい、難解な生き物だよ。」
掴んだままの手を逆に掴み返して、踵を返す。引っ張られた大倶利伽羅は立ち上がらなかったが、審神者はそのまま勢いよく左手を振り上げた。
「まだ秋でもないから何だろな、鷺とかかな。此処に居ない皆の分もね。
ゆく蛍 雲の上まで行ぬべくは 我ら壮健なりと鷺に告げこせ!」」
情緒もへったくれもない、まるでRPGの魔法の呪文のような詠みだったが、指先の淡光は迷わず飛び立った。
そして縁側に立つ2人の間を抜け、まだ中庭の池の上を彷徨う仲間を通り過ぎ、月明かりのない空に緩やかに溶けて消えた。
今剣が勢いよく振り返り、審神者の胸に飛び込んで来る。その勢いに流石の審神者も体制を崩したが、幸いにも彼女が尻餅を付いたのは、大倶利伽羅の太ももの上だった。2人分の体を難なく抱え込んだ彼は、眉間に皺を寄せていたが、特に文句は言わなかった。
ぐずぐずと今剣の鼻をすする音が小さく聞こえ、優しく微笑んだ審神者はそっとその頭を撫でてやった。
かつて最期まで仕えた主の名を、切なく繰り返す今剣をあやしながら、審神者はそっと後ろを仰ぎ見る。
無表情の顔は明後日の方向を向いていたが、その距離は物理的な意味でもそれ以外でも、今までで一番近い。
肩の力を抜いてその身を完全に預けると、抱え込んでいた腕がぴくりと揺れた。
「ちょっとーあんまりイチャつかないでよね。」
いつの間にか蛍丸が目の前で仁王立ちになって3人を見下ろしていた。
「はは、ごめんごめん。」と笑った審神者に、腕の中の今剣が漸く顔を上げる。
「よしつねこうにはちゃんと伝ったでしょうか?」
鼻の頭を赤くして、今剣が審神者の襟元をきゅうと掴む。
「ん。きっと大丈夫。仮に此処に来てなくても、さっきの蛍にお願いしといたから。今頃、いろんな鳥に伝言頼んでるよ。」
泣き笑いの顔で笑った今剣が、もう一度首筋に抱きついてから離れた。
「さっ、夕飯食べに行こう!流石にお腹空いたよ。」
「俺もー。」
「…はい!」
元気よく立ち上がった今剣越しに、自分も立ち上がろうとした審神者は、ばっちり誰かと目が合って止まった。
「うわ。」
思わず呻いた彼女の視線の先には、縁側の障子から顔を覗かせて、歯軋りしそうな勢いでこちらを見ている加州が居る。
「???全然来ないと思ったら???そんな暗がりで何してるの主???。何でそんな男に抱きかかえられちゃってんの?」
「ウザいよ清光。てゆうか、短刀達が一期に『主の部屋から蛍の群れが出て来るの見ましたー』って目を輝かせて報告してたけど。」
「うえーい。」
「ご飯冷めてるんだけど。まぁ随分仲良くなったみたいだから、お祝いで特別に温め直してあげようかな。赤飯炊く?」
「あらー燭台の奥さんまで。」
「誰が奥さんだい!」
「俺のことは遊びだったの?もう愛してないの?」
「もう飽きたよこの展開。」
「はいはい、ちゅうもーく!」
割と日常的な修羅場と化した部屋の中で、突如蛍丸が声を上げた。
「今、主は本丸に居る俺たち全員を必ず守ると口説いてましたー。よって主の愛は平等で、誰の物でもあり、誰か一人の物ではありませーん。」
「???あーうん、良かったね清光、愛されてるってさ。」
「???うぅ、本当?ん?でも皆同じ」
「あ、うん、勿論ですよ。めちゃくちゃ愛してるっちゅうねん。加州が一番可愛い。夕食後に爪デコってあげちゃう。」
「え、本当?嬉しい…俺愛されてるよな?」
「はいはい、そうだね。さっさと行くよ。」
「じゃ、俺らもお説教阻止に行こー。」
「もうこの間、一生分くらい怒られたのに…。」
「あるじさま、ちゃんとせつめいすれば怒られませんよ。」
「石切丸が来たら、俺が相手してあげるから。練度同じくらいだし多分勝てるよ。」
「うわぁ説得(物理)ってやつだね。阿蘇のお館様も安心して見守ってるわ。」
「まあね、任せといてよ。」
賑やかに縁側を一行が遠ざかって、暗い部屋に再び静寂が満ちた。
「さてさて、そちらさんはいつまで座ってるの?食器が片付かないから早く来てね。」
言うなり背を向けようとした燭台切に、大倶利伽羅は思わず問いかけた。
「あいつにとって俺達は何だ?ただの武器じゃないのか。」
「あいつって主のこと?うーん、それは本人に聞いてみないとあれだけど、家族っていうのが一番しっくりくるんじゃない?」
「???家族。」
「そう。短刀達が子どもで、彼女がお母さんで、その他がお父さん。あれ?一妻多夫みたいになっちゃうね。まぁその他は婿候補かな。ただし、参戦するならそれなりの覚悟が無いと到底 太刀打ち出来ないからね。」
「???そんな事は聞いてない。」
「あ、そう?ま、忠告はしたからね。赤飯ないけど早く来てね。」
今度こそ去って行った足音を聞いて、大倶利伽羅は畳に視線を落とす。
蛍の淡い光と、女の双眸の光、そして腕の中の体温と自分と変わらぬ心臓の鼓動が思い出された。
きゅるる、と何かの答えに行きつく前に、腹の虫が鳴いた。人の体とはつくづく面妖だ。
おもむろに立ち上がった大倶利伽羅は、遅れて縁側を歩き出す。目指す場所は光と喧騒に満ちていた。
中庭の木の葉の裏で、美しく儚い光が鼓動を刻んで、やがて飛んで行った。
 爱华网
爱华网



